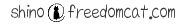2012年11月01日(Thu)
■ 『ピッケルを持ったお巡りさん』富山県警察山岳警備隊 編
1985年、山岳警備隊シリーズの中では一番、最初に出版されたこの本は、劔岳や黒部、立山といった難易度の高い登山エリアの救助に関する手記集だ。
ヘリでの救助も普及し始めたが、それよりも、人力救助や豪雪地帯ならではの冬山救助の事例が多い。
先に富山県警の本では『翼を持ったお巡りさん』を読んだが、この『ピッケルを持ったお巡りさん』の方が人力救助を主眼に置いているため、より遭難現場が生々しい。また、個人情報のあつかいにも大らかな時代だったため、要救助者の遺された同行者、身内の手記なども掲載されている。
とてもシリアスな事例もある一方で、コミカルでユーモアのある話もあり、お巡りさんといえど、血も涙もながす人間なのだと伝わってきたし、少し古い感じもするけれど、実直な山に対する精神が素直に出ている本にも思えた。
そして、山岳警備隊といっても、豪雪や落石の前には力が及ばないのが人間なのだという、人間らしい諦念があり、だからといって、登山をしてはならないという論にはよらず、登山を良いものとしているのは、山岳救助という分野ではあるけれど、山を愛する山男の一種であることが伺えた。
この本を読んで一番、良かったと思ったのは、「ヘリが教えた警備隊魂」という佐々木泉さんの手記だ。話としては、ヘリが活躍する山岳救助だけれど、搭乗出来ずにいつも現場に置き去りにされ、自力で下山することが多く不満もあった。ある時、天候が悪くヘリが飛ばないため遺体とビバークし辛い一夜を明かした。しかし、そこで立山連峰に朝日が昇る瞬間の美しさに出会った。そうしたら不満を言っていた自分が恥ずかしくなったという体験だ。
佐々木さんの手記によれば富山県警察では、山岳警備隊魂として、「苦しくても、苦しくない」「冷たくても、冷たくない」「重くても、重くない」と、ちょっと今の時代からみるとギョッとするような精神を受け伝えているそうだ。でも、山では苦しさや困難を超えた時に、自分が変わるすごい瞬間が待ち受けているのかもしれない。
ところで、この台詞どこかで見たような…と、思い出したら、漫画『岳』にしっかり出てきていた。10巻で、三歩が重い荷を担ぎながら言っていたし、探せばまだほかにもあったように思う。
この本にも、漫画『岳』の片鱗が、直接的な場面というよりも、山岳救助をする人たちの心の在りようとして、たくさんあって、読んで良かったと思った。
■ 『山靴を履いたお巡りさん』 岐阜県警察山岳警備隊 編
1992年、山と渓谷社より、山岳警備隊の本として二番目に出版されたこの本は、北アルプス飛騨側エリアの山岳救助活動をカバーする岐阜県警山岳警備隊の活動手記だ。
岐阜県警山岳警備隊は、1959年に誕生し、当初は富山や長野同様、民間救助隊に大きな協力を得、指導を乞いながら、徐々に山岳救助の技術を伸ばし、また、警察組織内でも隊員を増やし体制を整えていった。この時期、活躍したのは、鈴木釘夫氏(1937)、今井主憲氏(1947)、森本靖弘宏氏(1941)らである。
特に今井氏、森本氏は1960年代、民間救助隊からは警察警備隊が山でいったい何ができるのかと呆れられるほどの貧しい装備や技術を、がむしゃらに努力して、やがては民間救助隊と同等に連携し、さらには警備隊が独立して山岳救助ができるレベルまで、引っ張っていった警備隊内の実力者だったようだ。
1960年代の思い出話を読むと、隊員が集まって酒盛りをするとき、最後にはみんな裸になって円陣を組み、酔っ払いながらも山岳救助のあり方や技術について熱く討論したとか、登山屋にいって自腹で装備を揃える時に「いちばんいいピッケルを頼む」と、つい昨年だか一昨年だか前に流行った台詞そのままに頼み、一ヶ月分の給料が飛ぶような高価なピッケルを買ったりと、仕事という域を遙かに越えて、熱い思いを持って活動されていたらしい。
1975年には、現在も後輩指導に現役で活躍している谷口光洋氏(1956)が入隊し、隊は山岳救助活動に熱心に励んでいた。しかし、1977年5月4日、滝谷で二重遭難事故がおこり、長瀬隊員が殉死された。岐阜県警はこの二重遭難にショックを受け、滝谷での活動を自重するなど、山岳警備隊の活動に大きな制限をかけて、警備隊ができない活動は民間救助隊が担えばよしとした。
それまでは上昇志向だった岐阜県警山岳警備隊はこのとき、仲間の殉死のショック、組織からの圧力に力を落とし、活動が停滞気味になる。ちなみに、岐阜県警が本書を出すまでの殉死者はこのときの長瀬隊員のみで、毎年、丁寧な鎮魂参りが行われているのは、10/14に放映された谷口氏にスポットをあてた岐阜県警のドキュメンタリー番組でも紹介されていた。
岐阜県警は長野や富山の山岳警備隊と異なり、専門部隊ではなく、隊員がそれぞれ異なる業務を兼任したり、公務員として数年山岳警備隊を経験すると異動するといったデメリットもあったが、しかし、本書を読んでいると、力あり、熱意ある隊員によって、時には命がけの救助活動は、熱心に続けられていた。
この本に納められている数々の救助活動のエピソードは、北アルプス飛騨側の特性をあらわしていて、高い崖からの滑落、道迷い、そして豊富な水源が仇となりふだんはおだやかな川が雨による増水で荒れ狂い同時に何人もの登山者が命を落としたような事故など、さまざまなものがある。
そして、救助活動にあたるのも、警備隊だけではなく、後に配備されたヘリコプターの活躍や、提携する協力ドクターの活躍、また、山小屋経営者らいざとなれば民間救助隊となる人々との協同など、多くの人々のつながりがあってこそ、救助はまわってゆくということがわかった。
要救者にもさまざまな人が居て、1960-70年代には、山岳会などパーティーがかなりのところまで自力で遭難した仲間の救助をしようとする傾向があったが、道路や交通機関が整い出すにつれ、パーティーといっても、バラバラに行動するようなチーム力のない登山隊が増えてきたと記されている。
今は、もっと自己責任という題目のもと、パーティーがバラバラになる傾向に拍車がかかっていると思うので、パーティーのはずだったのに途中ではぐれ、単独で亡くなるケースなど増えているのではないだろうか。
登山の本を読んでいると、デメリットもあるけれど、やはりチームを組んで山をゆくことも、ひとつ登山の大きな醍醐味なのだから、今までの時代にない新しいつながりのチームでも、よりすばらしいチーム力を持って、登山をする時代にならないものかとわたしは思った。いや、わたしの伺い知らないところではもうそんなチームがいくつもあるのだろう。
もうひとつ、印象的だったのは、森本氏の発言なのだが、ヘリが導入されたことによるメリットデメリットだ。メリットとしてはもちろん危篤な要救者をあっという間に病院まで運べるというものがあるが、一方デメリットとして、遺体を収容した場合、麓で待つ家族の前にあまりに短時間に運びすぎるのではないかと危惧していた。
昔は人力搬送で、遭難現場から一日、二日と時間をかけて遺体を麓までおろしていて、その時間の中で、突然なくなった遭難者を受け入れる心の準備を家族は行っていたけれど、ヘリはその心の準備を行う時間を奪ってしまったのではないか、そして、その時間は案外、遺された家族にとってそれからを生きていくのに重要な時間だったのではないかとぽつりと記されていた。
それにしても、岐阜県警のこの本は、洗練された長野県警山岳警備隊や、霊山を多く頂き山に畏怖を持つ富山県警山岳警備隊と、少し性格がことなり、じつに人間として泥臭く、そこがいいのだ。たとえば女性の要救助者。若ければすれ違う一般登山者も手助けしてくれるだろう、しかしおばさんは誰も見向きもしないだろう。救助隊は仕事だからきちんと対応するけれど、といったことが書かれていた。
女性登山者(志望)かつ、これから中高年のレベルに入っていくわたしはなんだか悲しかったけれど、そういうこともストレートに書いてくれてあるので、遭難に対する心構えがきりりと引き締まったというのも事実だった。
2012年11月02日(Fri)
■ 『いのち五分五分』山野井孝有 著
2011年7月、山と渓谷社から出版されたこの本は、ギャチュンカンで下山中、雪崩にあい、脱出の過程で凍傷を負い手足の指を失うほどの困難な状況から生還した登山家・山野井泰史さんの父が、父の視点から息子の登山家としての生き方を記したものだ。
ギャチュンカンの登山は2002年のことで、この山行は2005年に作家沢木耕太郎氏が『凍』で詳細に記された。もうひとつ、山野井泰史さんご自身によるギャチュンカン含めた数々の山行をエッセイにした『垂直の記憶』もとても良い本だ。
『凍』にしても『垂直の記憶』にしても、メインは登山のことなのだけれど、その中で登場する、ギチュンカンではペアを組んで登攀された、山野井泰史さんの奥さんの山野井妙子さんが、異彩を放っていてとても気になる存在だった。
山野井妙子さん自身も日本のトップクラスの女性登山家で、アルパインスタイルで8000m峰四座に登っている。その中ではペアを組んだ相手を凍死で亡くされたり、凍傷で手足の指をなくされたりという体験も経られている。山野井泰史さんとの交際は、凍傷を負って帰国され、入院されていた頃から始まった。
山野井泰史さんについての本は、『ソロ』という本もある。この本は妙子さんについて、暗くて陰気な女だとか、そんな女を嫁にするとは考えられないといった悪し様な口調で書かれていて、読んでるこちらが不愉快に感じた。
『いのち五分五分』ではやはり障害のある女性との交際に消極的だった父が、二人が住む奥多摩の小さな古い家屋を訪れ、そこで、貧しいながらも、手仕事や地域の人々との交流を通して、豊かな暮らしをしているのをみて、妙子さんを心底認めてゆくのが、素晴らしかった。
この本の後半は、息子についてよりも、嫁の妙子さんについて、多くのことを記している。嫁の父フィルターがかかってるけれど、山野井妙子さんについて知るには貴重な本だと思う。*1
 ソロ 単独登攀者 山野井泰史 (ヤマケイ文庫)
ソロ 単独登攀者 山野井泰史 (ヤマケイ文庫)
山と渓谷社
¥ 998
*1 山野井妙子さんの登攀そのものについて、『いのち五分五分』では、さすがにそこまでは書かれてなかったけど、それは著者が登山家そのものではないので仕方ない。
2012年11月03日(Sat)
■ 『黄色い牙』志茂田影樹 著
1980年に直木賞を受賞したこの本は、大正末期から昭和18年、第二次世界大戦が始まるまでの時代、秋田県阿仁にあったマタギの集落を舞台に、その集落の最期のマタギの頭を主人公にした作品だ。(ただし、この作品はフィクションで、露留の里、露留峠といった地名は実在しない)。
どの程度までが事実かわからないのだが、この話は、マタギの生活、狩猟、伝統、信仰を主人公を通して豊かに描きだしている。
特に狩猟は圧巻だ。山奥深いマタギの里、さらに奥深く続く原生林で、シカリと呼ばれる頭の統制の効いた指揮のもと、獲物の追い立て役の勢子、仕留め役の射手ブッパが活躍する様がいきいきと描写されている。この集団狩猟は巻狩りと言い、実際にマタギが行っていたらしい。
マタギの狩猟の対象は熊で、巻狩りは、熊が逃げるときに斜面をかけあがる習性を利用し、勢子が「そーれアー、そーれアー!」と追い声をあげ、藪や林に潜む熊を追い立てる。出てきた熊をシカリが見張り、ブッパに向けて発砲指図のかけ声をかける。ブッパが獲物を撃ち取ると、「勝負!」と声を張り上げ、それが狩りの終了の合図となる。
この話はその巻狩りのパターンをうまく使っていて、読み終わったあと、なんとも言えない余韻が残った。
しかし、話は単純に大自然とその恵みの生活には終わらず、鉱山開発、世界大戦、不況、山の荒廃など、近代化の波がマタギの里山まで押し寄せて、代替わりしてゆくマタギの数は減ってゆき、その中で繰り広げられる人間の罪にまみれた諍いがなんとも悲しく、そして最期までマタギの誇りを捨てない主人公の存在が熱い。
『黄色い牙』作中と同時代の話では、『赤毛のアン』シリーズ、特に『アンの娘リラ』がかぶる。牧歌的な最後の時代から、世界大戦への緊張は同じだし、世代交代して大きく文化が変わってゆくうつろいも似ている気がした。あわせて読むと、『黄色い牙』主人公の娘の気持ちに奥行きがでる。ただし『黄色い牙』の方が生臭いので十代読者は注意。
著者の志茂田影樹さんはそういえば、ずいぶん昔から知っている。テレビのバラエティー番組でうかがうファッションはずいぶん人目を引くもので、10年も昔に麻布十番ですれ違ったことがあるけれど、テレビと変わらない格好をされていた。
また、最近はtwitterでもアカウントを持たれ、さまざまな人の人生相談に優しく励ます言葉を送られている。わたしもフォローしていて、傍目ながら、そんな言葉に励まされるところがある。(たまにあまりにも優しすぎる回答にそこまで優しくていいのかなぁ、と、思ってしまうくらい)
けれど、肝心の著作を読むのはじつは今回が初めてで、読み始めたらファッションやツイートの内容とはかけ離れた硬派な文体に驚いた。まだ三つの志茂田影樹さんが結びつかないような気もするが、マイノリティの側に立つ、強い優しさを持たれた方なのだと思う。
それにしても、わたしは、新田次郎さんや志茂田影樹さんのような、綿密な取材や調査に基づいた小説を今まで知らなさすぎた。読まなさすぎた。直木賞など有名な賞に入った作品や作家は、わざと遠ざけている部分があった。そんな自分の態度を反省した。もう少しまじめに小説というものが何であるかを読もう。
2012年11月05日(Mon)
■ 『空白の5マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』角幡唯介 著
角幡唯介さんは1976年生まれ、早稲田大学探検部のOBだ。地球上に遺された人類未踏の地は希少で、ツアンポー峡谷はそのひとつだった。角幡さんは在学中にツアンポー峡谷を探検に行くことを企画した。
そして、2002〜3年ツアンポー峡谷の未踏領域を単独探検、2008年のチベット動乱後、2009年再度ツアンポー峡谷に無許可単独で入り、寒波など厳しい状況の中、脱出した。その顛末を本書にまとめている。単なる顛末記に終わらず、本書の前半はツアンポー峡谷に挑んだ人々の変遷も丁寧に紐解いていて読み応えがあった。2010年、第八回開高健ノンフィクション賞を受賞している。
ツアンポー峡谷という聞き慣れない地名は、チベット高原の水脈が集まり、壮大な流量の川となり流れる地だ。グランドキャニオンをはるかにしのぐ規模らしい。チベット人も訪れないその秘境は、その昔、英国の探検隊が活躍していた時代に、最後まで全貌を見せず、1990,2000年代の冒険家たちが目指すにはうってつけの場所だった。
峡谷は密林や滝、絶壁など、困難な道なき道を越え、初めて到達できる。そして、その道中に潜んでいるヒル、ダニ、イラクサ、生息する植生や虫たちは、不快感を極める。ピークハント登山とは別種のルートファインディング的要素の強い山行を強いられる。
また、2002年には賄賂で進めたラサからの道も、2008年の動乱の影響で中国国内からラサへ至る経路は外国人を拒絶し、無事ついてもラサでの検問、また行く先々の村でも中国当局の影響に、おそれをなしているチベット人は協力を拒むといった障害が発生した。特に驚異だったのは携帯電話だという。
わたしはこれまで、チベットをゆく日本人の紀行を二冊読んでいる。ひとつは1995年の渡辺一枝さんの『チベットを馬でゆく』、これは、渡辺一枝さんがチベット人のガイドやコックを雇って、馬やジープを使ってチベット国内をぐるっとまわる話だった。日本との通信手段は手紙が主で、それも役所の機嫌次第で届かないものもあったという。
次に読んだのは『梅里雪山』で1991年の雪崩遭難のあと遭難者の遺体捜索のため10年間同地に通われた小林尚久さんの話だ。話の最後の方で、現地チベット人と携帯電話でやりとりしていた場面があったが、日本で応答したものだった。チベットという秘境だった場所と日本が携帯電話でP2Pで繋がれてしまうことには新鮮な驚きを得た。
どちらも2008年のチベット動乱の前で、多少の中国との緊張はあるが、それでも、牧歌的なチベットの風景が描かれていた。『空白の5マイル』は、ちょうどチベット動乱直前直後に二回、チベット内を踏み行った話としても興味深い。
2009年のツアンポー峡谷行きでは、角幡さんの場合、無許可で探検をしようとしていたのでなおさらだけれど、現地チベット人が携帯を持っていることが、通報の驚異だった。2002年にはチベット人にまったく問われなかった許可証の有無を、2009年には必ず問われ、チベット人たちは許可証の無い人間に関わったことが中国当局にわかれば投獄されるという危機感が強いことがうかがえた。チベットは動乱もだけれど、携帯電話というテクノロジーで、大きく変わってしまったことがわかった。
探検は人間文明が届かない地を分け入る要素が強いけれど、角幡さんの踏破した空白の5マイルを最後に、地球からは本当の未踏の地は失われてしまった気がして、読み終えたあと、達成感とも違う複雑な感触が残された。
これからの時代の探検や冒険について、角幡さんがたどり着いた結論は、一読の価値がある。
■ 『ミニヤコンカ奇跡の生還』松田宏也 著
標高7556mのミニヤコンカは、チベット高原東南を走る横断山脈の最高峰だ。チベット高原と四川省、雲南省、ミャンマーの境界となる横断山脈は多くの山脈から連なり、ミニヤコンカは横断山脈の大雪山脈にある。また、横断山脈にある怒山山脈には梅里雪山(カワカブ)がある。ちなみにツアンポー峡谷はヒマラヤ山脈の山系に属し、この横断山脈ではない。
Wikipediaによればミニヤコンカは1932年にアメリカ隊が初登頂したあと、1980年まで山域周辺は外国人立ち入り禁止だったが解除され、翌1981年、初登頂を目指した日本隊が8名山頂付近で4000mの滑落死という悲劇をおこしている。そのエピソードは本書でも一部明らかにされているが、『生と死のミニャ・コンガ』にあるという(未読)。それ以降も登頂成功者は20名に満たない難峰だそうだ。
『ミニヤコンカ奇跡の生還』は1982年、市川市登山会が6名の隊員でミニヤコンカを登山したが、最終的に著者の松田宏也さんと菅原信さんの二人がアタック隊として山頂を目指した。この話は、C5のテントを出発したあたりから始まる。
ミニヤコンカの難しさはいくつかあるが、ひとつは山頂付近の見晴らしの悪さ、何度も偽ピークが現れ、登山者の気をそぐ。また、めまぐるしく変わる天候。そして硬い氷と岩と雪。
松田・菅原ペアは山頂付近までは快晴に恵まれ、登攀できたが、山頂直下で時間と天候急変に追われることになる。そこからが暗転のはじまりだった。あと1時間という距離で山頂だったが二人は登頂をあきらめ撤退に入る。あきらめるまでの心理も詳細につづられている。しかし、そこからの撤退戦がすさまじいの一言に尽きる。
無線機の故障、食料不足、ビバークにつぐビバーク、吹雪、暴風、クレバス、乾き、ありとあらゆる困難が二人を襲い、C2でついに二人は別れてしまう。さらに下山を進める松田さんは幻視、幻聴にも襲われる。その間もパートナーを置いてきてしまった痛恨の念は筆舌しがたい。命からがらたどり着いたBCも、頼みにしていた仲間は二人の生存をあきらめて下山した後だった…。後二日、待っていればというタイミングだった。
その後、奇跡的に救出されたが、松田さんは63kgの体重が32kgまで落ち、重度の凍傷を負い、両手の指を切断、両足も膝下まで切断という結果になった。だが、松田さんはその後、義足をつけ、丹沢をベースに訓練を重ね、小西政継さんの隊でシシャパンマに挑み、今はスキーなども楽しまれているそうだ。
『ミニヤコンカ奇跡の生還』は、まるで小説を読んでいるような山行記で、松田さんの文学的な表現が登山の豊かさを饒舌に語る。あとがきでは「生きることはすばらしい」と、そして、希望を背負い直す決心をされている。それは安易な決心ではない。山男はどこまで強いのかと、深く感嘆した。
2012年11月07日(Wed)
■ 『山行記』南木佳士 著
2011年に出版された著書の登山に関するエッセイ集。著書は、芥川賞受賞作家であり、医師である。若い頃はカンボジアの難民緊急医療チームなどで働いたが、芥川賞受賞後、パニック障害とうつを発症。医師としては内勤の重度患者を受け持つポジションから、外来診療と人間ドッグを受け持つポジションへ変更した。
登山はそうして、時間ができ、また、うつ病の対策としてはじめたという。奥さんを伴って日帰りの山行を繰り返した体験、低山の森でも味わえる精神が落ち着く山歩きのことが淡々と綴られ、また、時には少し冒険とばかりに、数名の同業者とテント泊で、槍や豊島岳に訪れた体験も書かれている。
老齢の体力での、山歩きのよさがじんわりと爽やかな空気を生み出している。
先に読んだ、若さの体力の極限をめざすような登山はかっこいいなぁ、と、思うけれど、とてもおよびでない。少し肩の力を抜いて、体を動かすことで、「わたし」のバランスをとるような静かな山歩き、そんな山歩きを、わたしもしてみたいなと素直に思えた。
2012年11月08日(Thu)
■ 『山なんて嫌いだった』市毛良枝 著
美人は膝頭を決して崩さない。twitterで見かけた美人に関する分析だけれど、山で休む市毛さんの写真も、膝頭を美しく揃えていた。
わたしはここ最近、多少見るようになったものの、テレビやドラマにとても疎くて、市毛良枝さんという女優さんが山をやるというのは、先に読んだ山野井孝明さんの『いのち五分五分』で初めて知って、そして『山なんて嫌いだった』というタイトルに惹かれて手に取ってみた。
タイトルこそ山なんて嫌い…と言ってるけど、内容はお父様を亡くされてその病院の医師や看護師らに誘われて山へ行ってから、一目惚れと言って良いくらいの熱意で、忙しい女優業の合間を縫って、山通いされる楽しい話だった。
山を始められて二年目には田部井淳子さんとも出会い、登山されている。山での市毛さんと田部井さんのツーショット写真も掲載されていて、市毛さんの美しさと、そして女優さんと並んで同じくらい華奢な田部井さんに驚いた。田部井さんは今もテレビで大活躍されているけれど、スタイリッシュな山ガールと並んでも違和感ない細さは昔からだったのですね…。山に関係無さそうな関心だけど、登山はムキムキの筋肉マンよりも、体重の軽い人の方が有利なことを物語っていて、自分はダイエット頑張ろうと改めて決意した。
体力こそ一般人と変わらない市毛さんだったかもしれないけど、でも、女優というセレブな職業ゆえに、一緒に山へ行く人々も、行く山々も豪華で、うっとりする。
この書籍の執筆は1999年で、書籍後書きによるとこの執筆はヒマラヤ・ヤラピーク登山準備と並行して行われたと書かれている。また、2011年文庫化の後書きでは南アルプスを単独縦走されたとも記されている。もしあるならば、南アルプス単独縦走の山行記も読んでみたいと思った。
2012年11月09日(Fri)
■ 『生と死のミニャ・コンガ』阿部幹雄 著
1981年5月10日、7556mの山頂付近で、自分ひとりを残して、7名が一本のザイルに連なったまま落ちてゆく。声は発せず、恐怖と驚愕に見開かれた視線を残して。
著者の目の前で起こった悲劇を、なぜそんな結果に至ったのか、一年前の準備段階から予兆を記し、そして、事故後の15年の間の体験を織り交ぜて、敗因を徹底的に記す。
また、遺族に寄り添い、遺体発見できた場合の埋葬方法を探り、発見の知らせがあれば現地に赴き、遺族と共に現地の寺に葬る準備を重ねる。
人の死を、どこで区切りをつけて、遺された者は生きてゆくのか。人が人の死を受け入れることの複雑さ、重さを、ひとつひとつの足取りを通して丹念に描き出している。
この本は、2000年に上梓された。ミニャ・コンガから20年も経っている。しかし、頂上付近の出来事は鮮明で、著者はこのことを、何度も何度も何度も、強く思い返し生きてきたのだろう、それは大変、しんどいことだろうと思った。
■ 『エベレスト登頂請負い業』村口徳行 著
カトマンズの雑踏で日焼けした顔色の真っ黒な男に声をかけられる。「エベレストに登りたいのはお前か」。そして値段交渉がはじまる…といった展開かと思ったらまったく違った。
著者の村口さんは、日本人で一番、エベレスト登頂回数の多い方だ。職業は山岳撮影を得意とするフリーカメラマン。2011年に上梓されたこの本のあとがきで、これからNHKのグレートサミッツ隊で、エベレストへ行くと記されていたので、今年の正月にあった番組で、エベレスト頂上でカメラを回されていたうちのお一人だったのだろう。とても壮大な映像だった。
そんな村口さんは、過去にさまざまな人とエベレストへ同行している。一番最初に登場するのは野口健さんだ。
わたしがここのところ、登山ものにはまっているきっかけの一つは、ウェブでみたエベレスト山頂付近に放置されたままにある遭難者の遺体写真で、エベレストとはどんなところだろうかと興味を持った。
そして、検索してトップに引っかかるのは野口健さんのブログで、エベレスト登山について書かれたエントリは片っ端から読んだ記憶がある。
確かその中で、エベレストを始め8000mを越える山の登山には、高度順化といって、何度も少し標高をあげるところまで登ってはまた降りてきて体調を整え、また高い所に行ってと、2,3ヶ月をかけて徐々に身体を酸素が希薄な高度に慣らしてゆくことを知った。
村口さんの本を読んでいると、初めてエベレストへ臨んだ野口さんはこの方法を全く知らなかったそうで、村口さんは失敗を見守りつつ、エベレスト登山のセオリーを伝授したようだ。
他にエベレストの頂上付近まで、化石の採取に付き合った登山や、日本人女性最高齢の渡邉玉枝さんと登った時の話、また、冒険家三浦雄一郎さんの、70歳、75歳それぞれのエベレスト登頂に同行された話がある。いずれも耳にしたことのあるエベレスト登頂のエピソードで、それらの登山は村口徳行さんが裏方として支えられていたのだなと、よくわかった。
高度順化のタクティクスをどう組むかが一番楽しいという村口さんは、また同行者が安全に生きて帰るようにタクティクスを組むのも重要だとし、惜しまずに全ての話に、その時のエベレスト登頂のタクティクスを載せている。
また最後の章は「あなたの場合」として、これからエベレスト登頂する人にネパール側、チベット側両方それぞれのタクティクスの組み方を提案している。
わたし自身はエベレストに登るつもりはまったくないのだけど、再来年、芸人イモトがイッテQという番組で、エベレスト登頂を目指す宣言をしているので、その展開を予想して楽しむのに、この本は良い資料になるなと、ちょっとうれしい気分で読み終えた。
2012年11月10日(Sat)
■ 『信念 東浦奈良男 一万日連続登山への挑戦』吉田智彦 著
「自由 以降の出勤先は山となる。」
巻頭のカラー写真には、経年を物語る黄ばんだノートに、万年筆の腰のある文字で記されている。それは一万日連続登山を目指した東浦奈良男さんの日記だ。会社を定年で退職した翌日、1984年10月26日の日記だそうだ。
最初は富士山150回登頂を目指すトレーニングとして、三重の地元の山へ毎日通ったという。それが始まりだった。回数を重ねるうちにそれは連続登山一万日という目標に変わった。そして、衰弱で倒れる2011年6月25日まで、27年間、連続9738日、1万1951回の登山を行った。その半年後の12月6日、伊勢市内の病院で永眠される。享年86歳。
東浦さんが富士山以外、ふだん登っていたのは、いわゆる山岳記録の本が伝えるような山ではない。標高500m程度の無名峰を含める低山だ。だが、それを、毎日毎日、駅から取り付きまで3時間市街地を歩くのも含め、続けられた。そして膨大な日記も残された。
ライターの吉田智彦さんが東浦さんの取材を始められたのは8000回登山後、一万日達成を見据えた2006年からだ。当時、山と渓谷の副編集長であった勝峰富雄さんが東浦さんの登山に注目し、多忙な自分の代わりにと吉田さんに東浦さんの登山を追うライターとして白羽の矢を立てたという。
吉田さんは東浦さんの取材を始め、そして日記の存在を知る。私的な内面まで立ち入る日記というものを、果たして読ませてくれるかどうか、おそるおそるお願いしたところ、東浦さんは快諾してくださったそうだ。
東浦さんは耳が少々遠くなり、インタビューが難しかったという。また、口頭の応答は端的な言葉で、心を割って話す表現からは距離を置いてられたようだ。だが、それを補ってあまりある、東浦さんの登山を、吉田さんはこの日記を読破することで、得た。
そのため、本書は、取材を始める前の東浦さんの登山までも、日記から抜粋という形で豊かに記している。東浦さんの文章は、他人に読ませることは前提にしていないものの、独特なユーモアと個性があって、吉田さんの地の文のサポートもあり、読みやすい上、なおさら、迫ってくるものがあった。
東浦さんは表紙から見て取れるように、粗末な、乞食とも勘違いされるような身なりだった。だが、日焼けし、老齢の皺が刻まれた顔は意志がある。どちらにしても、正直、自分がこの人とすれ違ったら、風体から、次にその精悍な顔立ちに気づいたとしても、怖いと思い、道の逆を行くと思う。
けれど、この人は、幸せについて本当の幸せを知っている人だった。
'' 「神は与えるもので、与えられることが幸せ。幸福とは与えられることでなくして、他に与えられることのできる者である。幸せとは人に与え、万物に与えられるものを己れに持つことなり」一九九五年三月二十五日
東浦さんの一万日連続登山の理由は、宗教的なものや、名誉欲や自分のためといった功利的なものではなかった。ただ山に登るのが好きだった。そして、"山を登ること"しか、こどもにも、亡くなった父母にも、そして、病に倒れた妻にも、与えることができなかった。
そんな生き方もあるのかと、わたしはこの本を読み終えて、涙を流した。わたしのここに書ける言葉は拙いので、ぜひこの本は興味が湧いたら手にとって、読んでもらいたい。お勧めの本だ。
2012年11月11日(Sun)
■ 『ドキュメント 雪崩遭難』阿部幹男 著
科学的知識をもって雪山に臨むこと。経験と勘で「ここは雪崩が起こらない」と思いこまないこと。1997年から2001年までに発生した8件の雪崩遭難を事例とし、どのような場所や状況で、雪崩遭難が発生したかをレポートしているのがこの本だ。
雪山での雪崩は、弱層雪崩と全層雪崩の二種類がある。本書では特に弱層雪崩の被害事例の方が多かった。弱層雪崩とは、たとえばあられやみぞれまじりの水分の多い雪が降ったあと、さらに降雪が続き、表面的には安全な積雪に見えても、下にもぐったその層が加重などの要因で、流れだし、上に積もった雪もろとも流れていく。これは弱層テストといい、掘った雪の層の断面の観察によって、雪崩そうな積雪状態は判断できるそうだ。
雪崩にあわないための弱層テスト、そして、もし雪崩にあってしまった場合の装備として、スコップ、ゾンデ(埋まった人を探るための棒)、ビーコンは、スキー、スノーボーダー、登山者問わず、雪山の必需品としていた。
これらの方法や器具の扱い方は講習で拾得するしかない。だが、講習を実施する側のプログラムについても、机上講習で実感と結びつかず、せっかく講習を受けたのにその知識が雪山で実践されずに起きた事例もあった。著者は冷静に、今後の講習の改善についてもふれていた。
この本の著者の阿部幹男さんは、先に読んだ『生と死のミニャ・コンガ』の著者でもある。中国にある7000m級の山の頂上付近で目の前で、一緒に登っていた8名の仲間を一気に滑落で亡くされた。その経験の恐怖から、登山自体はやめてしまわれたが、地元北海道での山スキーは続けられ、山の不幸を減らすために、雪崩について啓蒙活動をはじめられた。
この本は、その雪崩についての啓蒙活動の一環として刊行され、事例レポートとなっているが、雪崩についての科学的知識や救助方法そのものは『決定版 雪崩学』が詳しいらしい。
また、著者は、自分自身の仲間を亡くされた経験をふまえ、生還者のインタビューを慎重に行っているのも印象的だった。生還してから日が浅いうちは、本人のショックも大きいことを実感として知っている。けれど、なぜ失敗したのか、そのミスをインタビューを通してさぐらないと今後の雪崩遭難に生かされない。時に遭難事故のから何年も置いてからようやく、生還者にアポイントを取られるなど、慎重な配慮がなされていた。
そのため、事例は単純に雪崩遭難が起こりました、科学的にはこのような理由です。対策はこうすべきでした、と、いった通り一辺倒な説明には終わっていない。雪崩前、どんな気持ちでその斜面にいたのか。事故後にはどうだったのか。特に生還者がその後、山スキーや登山をどのように続けたのか、それとも止めたのかまで言及し、それぞれを受け止めている。
ところで、わたしは漫画『岳』でこうした山の遭難やレスキュー活動に興味を抱いて、こういった本を読んでいる部分もあるのだけれど、この本にも、やはり、『岳』の主人公三歩の片鱗があった。
たった一人で雪山に何日も入り、雪洞生活をし、雪崩にも関心があったので気象と着氷の観察を続けられている人が居た。一週間に一度、近くの山荘に降りてきて、お風呂に入り、人との交流も大切にしていた。残念ながらこの方も、一人で居るときに雪崩にあい亡くなられている。約束した連絡がないことを不安に思った友人が訪ねていったことで、雪崩遭難が発覚したのだった。
2012年11月12日(Mon)
■ 『聖職の碑』新田次郎 著
大正2年8月26日、信州の伊那の里にある、尋常高等小学校の生徒ら37名が、伊那駒ヶ岳に向かい、天候が急変。11名の死者を出した。実際にあった遭難事故である。
これを題材に書かれた小説がこの『聖職の碑』だ。最初、わたしはこの小説を読むかどうか迷った。最初からわかっている悲劇。文庫本のページを繰るとすぐに、山の地図に、誰がどこで亡くなったかという×がついている。小学生の子を持つ親として、やはり、こどもが亡くなる話はつらい。どうしようか。どうしようか。迷いながらも、ページを繰り始めた。
話は大きく3部の構成で、そしてさらに1章分、著者の取材記がついている。1部は山へ行く前。登山を実施する学校の校風が、実践教育を教育の基とする赤羽校長と、新しい洋風な思想である白樺派を基にした自然教育を行いたい若手の教師たちとの、それぞれの理念が出会い、とまどいながらも、こどもたちを第一に考えて本当に良い教育を行いたいという思いのもと、前向きに描かれていた。
登山は、思想がどう揺れ動こうが、体験が人間を作る基礎となるという実践教育に重きを置く、赤羽校長から提案され、3回目の実施だった。教員や父兄の中には、修学旅行に3000m級の山行は厳しすぎるのではないかという批判もあったが、それでも、下見を遣い、持ち物、装備を丁寧に指導し、OBの青年会も同行する手はずを整え、観測所にも天候について問い合わせ、入念な準備をすることで、決行に至った。
ところが時代は大正2年、1913年である。装備も雨具は茣蓙や合羽、足下は草鞋。今のように羽毛のダウンやゴアテックの雨具があるわけではない。また天気予報も、今のように高気圧、低気圧、雨雲や台風進路がグラフィカルに描かれるものではない上、当時は台風という概念もなかった。台風はただ、韋駄天低気圧という低気圧でも強いものという認識だった。
2部は登山が開始され、一日目の目標の小屋につくあたりから暗雲が立ちこめる。麓では雲行きが怪しい程度だったのが、標高があがるにつれ強風となり台風が近づいてきたのだ。そこからはもう、壮絶な気象遭難の描写が続いていく。著者新田次郎氏は、富士山気象観測所にも勤務した経験があり、下界からは到底、想像もつかない山頂の嵐のさまをリアルに描写していくのだ。
そして、一人が倒れ、パニックを起こす集団…。あとはここで一人、ここで二人と、こどもたちが亡くなる様が痛々しい。最後まで力をふりしぼり、赤羽校長と付き添いの教員の、必死でこどもたちを守ろうとする極限の戦いもまた、つらい。結局、赤羽校長は、救助隊が来るまでは息があったものの、すぐに現場で息を引き取られてしまった。
3部は一人の教員が麓の村まで救助を要請に走り、救助活動が繰り広げられるところから、父兄の怒りが学校へ向かう対立を描く。また、現在も本当にある遭難碑の建立に奔走し、赤羽校長の教育理念を残すことに信念をかけた教員を描いている。
37名中11名が死亡する大遭難事故。現代ならば、このような事故があれば、学校は登山教育を中止するだろう。しかし、信州の周りは山に囲まれた伊那の里。山は暮らす人々にとって、分かちがたいものなのだ。そのため、しばらくは中止されていた登山も、やがて再開され、この事故を教訓に、登山を前提にしたカリキュラムが組まれ、現在もそれは続いているという。現在のカリキュラムは取材記に詳しく記されている。
ところで、わたしはこの本を読み終えて、自分を振り返り残念なことがあった。もっと前にこの本を読んでいれば。わたしはこどもを就学前に山へゆくカリキュラムをいれたところに通わせていた。この時のカリキュラムは駒ヶ岳のような高い山ではなく、穏やかな里山に続く低山だけれど、こどもたちが伝書鳩を持って登山してそこから放つというものだった。もし、この本をそれをする前に読んでいたら、教育と登山の意味の大きさを知り、もっともっと深い心で、こどもを送り出せただろうに。
2012年11月18日(Sun)
■ 『ザイルを結ぶ時』奥山章 著
1926(大正15)-1972(昭和47)、戦中派の登山家、奥山章は岩と氷の壁に挑むアルピニズムを提唱実践した。これは、後にヒマラヤ鉄の時代と呼ばれる代表的登山家、小西政継に引き継がれる。
奥山は学徒動員前後には丹沢通いをし、青年期にはボルトやハーケンを利用した登攀を繰り広げ、異端と呼ばれるRCCⅡという山岳同人を立ち上げる。
登山と山歩きを明確に区別し、登山に厳しい理想を描いた。そして、その理想を他者が安易に共感することを拒んだ。厳しい人だ。
ボルトを使った登攀は岩を物理的にえぐるため、環境破壊を指摘され、現在は一線を退いた登攀方法だが、当時は画期的で、『岳人』や『山と渓谷』といった山岳雑誌から注目され、たくさんの寄稿をした。
この本はそうした寄稿と死後整理された未発表の遺稿から成る。戦中、戦後と登山が盛んな時代、日本の前衛的アルピニズムを知るには最適な本だ。
また、日本女性で初めてマッターホルン北壁を登攀した今井通子隊にカメラマンとして同行のエピソードや、ソ連の登山学校の視察、シャモニーなどヨーロッパの登山状況のレポートなど、内容は濃い。
今井通子のマッターホルンについてはまた別に本人の山行記があるのでそちらをあわせると読者はひとつの登攀を複眼的な視点で知ることができる。
ソ連の登山学校視察のレポートは、1996年のエベレスト大量遭難の時に活躍したガイド、ブクレーエフのバックグラウンドが垣間見れる。ソ連の共産主義は批判されるものもあるが、すべてがマイナスではなく集団行動が必要とされる登山など、文化的なスポーツには科学的で合理的な手法を盛んに導入し、質の高い訓練法を築いていたのだと、改めて知らされる。
しかし、厳しい話ばかりではなく、時にはこどもを伴って涸沢に何日もキャンプし登攀した話や遠征先からの奥様への手紙など、家族への愛情も記されていて、前衛的一辺倒ではなく良かった。
だが、奥山はヒマラヤ遠征メンバーに選出された直後に癌が発覚。癌を苦にし、自殺された。
 ザイルを結ぶとき (yama‐kei classics)
ザイルを結ぶとき (yama‐kei classics)
山と溪谷社
¥ 1,890
■ 『女性ガイドのしなやか登山術』樋口英子 著
何の気なしに手にとってみたら、想像よりも面白かった。
雪山、沢、岩登り、テント泊にビバーク演習。それらの初心者ガイドをしたエッセイで、装備や技術のことよりも、楽しむコツや山そのものの描写に重きが置かれている。
取り上げられている山域も、奥多摩や丹沢が多く、身近なためか、行けそうルート、無理そうなルートどちらにせよ、より具体的に想像が膨らんだ。
また、中高年のハイキングではなく、もう一歩、突っ込んで山に挑みたい場合は、やはり著者が開催しているような山行に入門するのが良さそうだなと思った。
おそらく著者の山行には、初心者といっても、まるっきりの初心者ではなく、ある程度意志を持って日ごろからトレーニングをして、体力を作っている人が望まれていると思う。体力のないわたしにはまだまだ先だ。
あとがきをみたら、雑誌『岳人』に連載されていたものだった。だからこんなに山に本気なのね、と、納得。岩、沢、雪山…。遠い世界だけれど、やっぱり良いなぁ。
2012年11月19日(Mon)
■ 『63歳のエヴェレスト』渡邉玉枝 著
元神奈川県職員で、日本人女性最高齢でエベレスト登頂記録を二度も更新している渡邉玉枝さんの著書を読んだ。謙虚な方で、一般ルートから登ることなど、大したことではないと書かれている。読み始めてみると、すばらしい健脚の持ち主であることがすぐわかる。
この本は63歳でエベレストに登頂するまでの渡邉さんの山行を振り返ったものだけれど、マッキンリー、マッターホルン、キリマンジャロ、アコンカグア、チョー・オユー、ダウラギリⅠ峰、ガッシャーブルムⅡ峰、天山山脈ポベーダ、パミールのムズターグ・アダ、エヴェレストと、溜め息の出るような山行を重ねられている。
そして、その合間に、地元神奈川の丹沢の山行がちらりちらりと出てくるので、そうか、世界の山を歩く人の足はあのルートからここまでを冬の時期に抜けてしまうのだな、と、やはり溜め息がでる。
28歳から登山を始められた渡邉さんは一貫して自分を一般の登山者と位置づけていらっしゃるが、そもそも登山の始まりが違う。一般のハイカーは山岳会に入っていきなりの冬の谷川岳には行かないだろうし、日本で訓練を積んだといって初めての海外遠征でマッキンリーの氷の岩壁を登るルートには行かないだろう。渡邉さんはそれをされているのだ。
渡邉さんは健脚だ。1987年の正月に行った前穂高岳の下山時には、時間の都合で急ぎ足で何人も追い抜いかれたエピソードがある。そんな渡邉さんを唯一追い抜いたパーティーは山岳同志会の人たちだったという。ちょっと素人のわたしには女性の足で、唯一抜かされたのが山岳同志会だけという速さが想像つかない。
その健脚も世界の名だたる山を登ることのできた一つ大きな理由だけれど、もう一つ、この豪華な山行には理由がある気がした。それは、文章のはしばしから滲み出る渡邉さんのお人柄だ。
自分の足で安定して歩き、そして人柄も良い。山行に誘いたくなるような方なのだと思う。最初の谷川岳も、マッキンリーも、そして、エベレストも、渡邉さんは誘われている。誘われるというのは、すごいことだと思う。
そこで、渡邉さんは自分が女性で、一般と変わらない、でも、与えられたチャンスを感謝して受け取りその中で最善を尽くしてゆく姿勢を崩さない。周りとのお互い様でのやり取りを大切にされる。そして一つの山ごとに確実に登頂し下山してくるのだ。
ちょっと真似できる感じがしない。街中のおばさんが山にちょっと行く流行りの中高年登山とはまったく違う。清々しいまでに、うーん、この人、すごい!と思える本だった。
ところで、イモトと同じく、マッターホルンはヘンリル小屋からガイドと一緒に登られている。4時間50分で登頂。ヘンリル小屋までの下山は1時間40分。ヘンリル小屋からの往復トータルは7時間。午前4時30分から登り始めたので午前11時30分に戻られている。日本からの一般ツアー参加だったが、同じツアー参加者で一番遅かった人は午後4時近くとのこと。
この時、岩登りは素人とガイドに伝えてらっしゃるが、その前にマッキンリーのアメリカン・ダイレクト・ルートをこなしているので、騙されてはいけないのだ。
2012年11月21日(Wed)
■ 『芦峅寺ものがたり 近代登山を支えた立山ガイドたち』鷹沢のり子 著
立山の麓にある芦峅寺の人々が、江戸時代から、どのように山との関わりを持ってきたかを辿ったのが本書だ。2001年刊行。
芦峅寺の人々は、江戸時代の山岳信仰の案内人、狩猟採取、劔岳開山後、学術登山隊などの山岳ガイド、ヒマラヤ遠征隊の縁の下の力持ち、そして富山県警山岳救助隊につながる民間山岳救助活動、山小屋管理業。南極越冬隊の活動隊員としても活躍した。
時代の変遷にしたがって、ガイドから救助隊へ、そして、山小屋管理人と仕事は変わったが、険しい山々と共に暮らす実力派の芦峅寺。
芦峅寺は、新田次郎の『劔岳 点の記』に登場するし、『ピッケルを持ったお巡りさん』の富山県警山岳警備隊創設時、民間救助隊として技術指導や活動そのものを支えた。またこの本では触れられていなかったが、『63歳のエヴェレスト』(2003年刊行)によれば立山エヴェレスト友好協会という組織が芦峅寺にあり、ヒマラヤのクムジュンと交流し、シェルパが何人も研修に来るらしい。
日本の登山史に不可欠な拠点である芦峅寺の歩みを、この本では俯瞰することができた。
2012年11月23日(Fri)
■ 『百年前の山を旅する』服部文祥 著
すごく良かった。なぜ、わたし自身が登山文学に惹かれるのかわかった気がした。端的に言い表されている箇所があった。
この本は七つの山行からなる。山岳雑誌『山と渓谷』初代発起人、『岳人』初代発起人、また、大正元年(1912年)の宣教師の、それぞれの追跡山行。若狭から京都まであったと言われる鯖街道、また、江戸時代の黒部奥山廻りの発掘山行。そして、北アルプスで見つけた一つの火器を巡っての過去から現代への探検に関する思索山行。
どれをとっても興味深いものだったが、わたしが一番面白かったのは、古文書に描かれていた江戸時代の黒部奥山廻りが、本当に実施可能だったのか、その道を発掘する目当てで分け入った山行だ。
道を発掘といっても、いわゆる峠道のように踏み固められた道は、最初から期待されていない。古文書の地図と、現代の地図を照らし合わせ、そして、実際に著者が当時の装備を出来る限り真似て行動し、人が辿れるかどうかを追試するのだ。
古地図は、現代の測量の行き届いた地図とは異なり、人の認知や解釈が大きく入り込む。著者が現地を辿りながら古地図に描かれたいにしえの人々の心理をも掘り起こすのが、なんとも言えない迫力があり、良かった。
そして、巻末には、それぞれの山行について、参照した本と、その本の簡単な解説もあった。その文献を元に新たな山岳文学に触れるのも良いだろう。だが、本書の山行は、文献を読み、そこから得た過去の事実と現代の自分を繋ぎあわせるための山行というパターンになっていることをここから読み取ることが大切な気がした。
この本は折に触れて思い返し、読み返す本になりそうだ。
2012年11月24日(Sat)
■ iPod touch 5th 64GBを手に入れた。
手元にあった4thの電池がだいぶへたってしまったことや、新しいiPodのカメラ画素数が500万画素と大幅に向上していることなどから、どうしても誘惑に打ち勝てず、iPod touch 5thを購入してしまった。買わない予定だったのだけれどなぁ。おかしいなぁ。
初めてのiOS機種の機種変で、データの移し替え、どうなるのかと思ったら、iTunesに古い方を接続し、バックアップ、新しいのを接続し、復元、という手順を踏んだら、メールやEvernote、Dropboxなど一部のアプリのユーザパスワード認証を除いて、ほぼそのまま移行できてしまった。なんと便利なことだろう。
![]() 最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 64GB ブラック&スレート MD724J/A
最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 64GB ブラック&スレート MD724J/A
アップル
¥ 32,262
2012年11月25日(Sun)
■ 『K2 2006 日本人女性初登頂・世界最年少登頂の記録』東海大学K2登山隊 編
2006年、日本人女性でK2を初登頂した女性がいる。小松由佳さんという。わたしが初めて存在を知ったのは、14座登頂を果たした竹内洋岳さんのブログで、竹内さんがガッシャーブルムⅡ峰で雪崩にあった時、現地まで支援に駆けつけたエピソードだ*1。
パキスタンにいる大けがで入院した登山家のもとへ、支援のためにさっと駆けつける。どんな女性なんだろう?と、調べてみたら、その前年に世界でもっとも登頂が難しいと言われる8000m峰のK2に、日本人女性で初登頂を果たした方だった。
どんな女性なんだろう?どんな登山家なんだろう?K2へはどんな風に登られたのだろう?
ところが。小松由佳さんはなぜか手記本が存在しない。ウェブにも文章がほとんどない。現在、山岳雑誌『岳人』で連載を持たれているようだけれど、どちらかというと登山よりも世界旅行系のエッセイのようだ。
小松由佳さんのK2の話を、もう少し詳しく知りたい。いろいろと検索してみたところ、本書の存在を知った。もしかしたら、この本に詳しく手記があるかもしれない。そう思いながら、遠方の図書館から地元の図書館のリファレンスを通して、本を取り寄せてみた。
わかったのはこんなことだった。
小松由佳さんは東海大学山岳部OGで、K2登山隊は、東海大学山岳部顧問の出利葉義次氏が企画、隊長を努められた。また、東海大学は医療、スポーツ、気象などのアカデミック資産を所有した総合大学で、この東海大学K2登山隊は、高所トレーニング、高所気象予報、現地医療スタッフなど、総合大学の力で科学的にどこまで挑めるかを挑戦する側面が大きかった。本書はその総合的な報告書で、会計報告、装備一覧、スケジュール、タクティクス、気象予報、医療活動などが、わかりやすく記されていた。
しかし、無味乾燥な報告書ではなく、なんというか、はしばしから人間味があふれ出ている。登山隊というと、どこか精神的に追いつめられ、人間関係にひびが入り、ぎすぎすしたような雰囲気もあるのだけれど、この本の登山隊の人々は、そこが良い意味で抜けている。終始、ほんわかしたムードで、隊員全員が仲良く、また、BCで一緒だった別の登山隊ともなごやかで、現地の高所ポーター、コックらも丁寧に紹介している。
それは、結果的に、隊員全員が、無事に帰国できたことにもよるだろうけれど、ちょっと今まで読んできた登山隊にはない雰囲気でおもしろかった。
もうひとつ、このおもしろさは、「登れちゃいました!」という驚きにもある。この登山隊、当初は、東海大学山岳部OBの登山家、平出和也氏がアタック隊の柱として期待されたという。しかし、平出氏はこの登山の前に凍傷を負い、残念ながら支援隊という後方にまわった。そして、次に期待されたのは、実際にC3までのルート工作やキャンプ設営に精力的に励んだ、OBの蔵元学士氏だ。ところが、蔵元氏はアタック開始のためBCから出発した直後、虫垂炎のような激しい腹痛に見舞われ緊急下山してしまうこととなった。
おそらく、その時、登山隊のほとんどの意識は、もうそこでK2への挑戦への期待は終わったのではないか。リーダーの蔵元氏の急病による下山。ヘリの手配。ヘリが来られる位置まで、担架に乗せての移動。アタック隊に残ったメンバーは、OGの小松氏、学部4年生の青木氏の2名。隊長は、もしかしたら…わたしの勝手な憶測なのだけれど…、二人は適当なところで引き返してくるのではないかと、思ったかもしれない。ここまで来たのだから、二人納得の行くところまでやってこいと、判断を若い二人にゆだねて、登山を続行させたのだ。
そうしたら、まさかの登頂。
小松氏の隊員紹介にはこう記されている。
頂上アタックも、幸いなことに無線が通じず、うるさい隊長から離れて自分の世界で登り続けた。
なんともコミカルに紹介されているが、記録をみると相当、あぶなかったようだ。
2006/8/1 午前2時30分、C3からアタック出発。午前3時30分の無線交信後、連絡がとれなくなる。夕方4時50分、登頂成功の無線連絡が入る。午後5時50分、下降開始の無線連絡から再び無線連絡がとれなくなる。
エベレストの場合、午後1時、遅くとも2時には登頂したにせよ、しないにせよ、下山を開始しないと、それは命の危険を意味するという。K2の場合はなおさらだろう。それが、午後5時50分に下降開始だ。
BCの隊長、隊員らは登頂成功に湧いたものの、すぐに遭難の大きな不安に包まれる。日本では大学が遭難の緊急対策本部をマスコミには秘密裏に設置したという。
小松氏のアタック報告によれば、8/2、午前2時に8200m地点で酸素が切れ、ビバーク体制に入ることとなった。無酸素で、8200m地点でのビバーク。おそろしく危険だ。だけれど、報告は気力にあふれ、決して危険を感じていないのが不思議だ。
それは、高所トレーニングによって高所に順応できていた成果もあるだろうし、日本からの気象情報支援で快晴時を的確にスケジュールできたことにもあるだろうし、また、アタック開始前後から血管の働きをよくするために飲んでいたビタミンEにも支えられたかもしれない。
そうして、夜を明かした、小松氏の報告には8200m地点の夜明けが、ダイナミックに描かれている。十分な朝陽のぬくもりに照らされて、ふたたび力を得て、出発し、8/2 午後12時30分、無線予備機が置いてあるC3に、二人は無事帰還し、BCと連絡がとれた。日本の遭難対策本部が公式に消息不明を発表する寸前だったという。
報告書によれば、C3でも体力回復のために一泊したようだが、その時、小松・青木の二人はそろって不思議なことを体験した。標高7800mのC3。しんと静まりかえって、誰もいない世界のはずなのに、テントの外から、外国人の話し声が聞こえたというのだ。そっと語りかけるような声だったという。小松氏はこのテントを出てはいけない。そう思ったそうだ。K2には多くの遭難者が眠っている。
凍傷も負わず、落石に大きな怪我もせず、無傷で、本当によく帰ってきた。
2012年11月30日(Fri)
■ 電池の消耗したiPod touch 4th を修理にだしたら新品交換、新規保証が9ヶ月ついてきた。
5thを手に入れて、完全にそちらに乗り換えてさて、4thをどうするか。ふと、この日記のiPod touch タグを振り返ったら入手したのが2010年12月だった。AppleアカウントでApple Care の確認したところ、12月上旬まで、保証がある。
これはまだ保証きくかも?!と、横浜駅西口にあるカメラのキタムラにもっていった。カメラのキタムラはApple正規プロバイダーとなっていて、Apple製品の故障受付をしてくれてるのだ。これは便利。
持ち込む前に4thは初期化してデータを消去。もしかしてこれで電池がやや復活し、有償になるかな?と一抹の不安もよぎったけれど、やはり店頭で、電池残量が不安定な動きを見せてくれたので、即無償交換となった。
交換は、1日かかり、翌日、引き取りに行ったけど、Apple Care を無駄にしないですんで、ちょっとうれしかったな。
■ iPod touch でtumblrにquote post する環境がようやくできた。
ここ一年くらい、足が遠のいていたtumblrだけど、いくつかのアプリを入れて、ブックマークレットを設定したら、PCと同じとは言えないまでも、だいぶ楽にquote post ができるようになった。
用意するのはフルスクリーンブラウザ LibingとNote & Share(広告入りの無料版もあるらしいがわたしは試してない)だ。
- フルスクリーンブラウザ Libing
https://itunes.apple.com/jp/app/libing-fullscreen-browser./id503189411?mt=8
- Note & Share
https://itunes.apple.com/jp/app/note-share-li-funa-lian-xie/id391714522?mt=8
見ているウェブページからtumblrにquote post するには引用文と引用元タイトル、urlの三つをコピーする必要がある。
次のブックマークレットは、Libingで開いたページの中で、引用範囲を選択すると、SelectMenuからボタンひとつで、Note&Shareに、この三つを転送してくれる。そうしたら、Note&Shareからtumblrの自分のアカウント宛てにメールをすれば引用投稿ができる。
javascript:(function(){var t=document.getSelection();if(t!=''){location.href='sharemore://note/- '+encodeURIComponent(document.title)+' '+encodeURIComponent(document.location.href)+'/"'+encodeURIComponent(t)+'"';}})();
Libingにブックマークレットを保存する時、"Select Menu " を指定する。
本当はこのブックマークレットから直接メーラーを起動させる方がスマートなのだけど、まだうまく動かせない。
Libing は検索ハブと組み合わせるとよりしあわせにもなるし、ウェブ上のGoogleMapをフルスクリーンで表示もしてくれるので、とても良い。