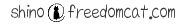2012年11月01日(Thu)
■ 『ピッケルを持ったお巡りさん』富山県警察山岳警備隊 編
1985年、山岳警備隊シリーズの中では一番、最初に出版されたこの本は、劔岳や黒部、立山といった難易度の高い登山エリアの救助に関する手記集だ。
ヘリでの救助も普及し始めたが、それよりも、人力救助や豪雪地帯ならではの冬山救助の事例が多い。
先に富山県警の本では『翼を持ったお巡りさん』を読んだが、この『ピッケルを持ったお巡りさん』の方が人力救助を主眼に置いているため、より遭難現場が生々しい。また、個人情報のあつかいにも大らかな時代だったため、要救助者の遺された同行者、身内の手記なども掲載されている。
とてもシリアスな事例もある一方で、コミカルでユーモアのある話もあり、お巡りさんといえど、血も涙もながす人間なのだと伝わってきたし、少し古い感じもするけれど、実直な山に対する精神が素直に出ている本にも思えた。
そして、山岳警備隊といっても、豪雪や落石の前には力が及ばないのが人間なのだという、人間らしい諦念があり、だからといって、登山をしてはならないという論にはよらず、登山を良いものとしているのは、山岳救助という分野ではあるけれど、山を愛する山男の一種であることが伺えた。
この本を読んで一番、良かったと思ったのは、「ヘリが教えた警備隊魂」という佐々木泉さんの手記だ。話としては、ヘリが活躍する山岳救助だけれど、搭乗出来ずにいつも現場に置き去りにされ、自力で下山することが多く不満もあった。ある時、天候が悪くヘリが飛ばないため遺体とビバークし辛い一夜を明かした。しかし、そこで立山連峰に朝日が昇る瞬間の美しさに出会った。そうしたら不満を言っていた自分が恥ずかしくなったという体験だ。
佐々木さんの手記によれば富山県警察では、山岳警備隊魂として、「苦しくても、苦しくない」「冷たくても、冷たくない」「重くても、重くない」と、ちょっと今の時代からみるとギョッとするような精神を受け伝えているそうだ。でも、山では苦しさや困難を超えた時に、自分が変わるすごい瞬間が待ち受けているのかもしれない。
ところで、この台詞どこかで見たような…と、思い出したら、漫画『岳』にしっかり出てきていた。10巻で、三歩が重い荷を担ぎながら言っていたし、探せばまだほかにもあったように思う。
この本にも、漫画『岳』の片鱗が、直接的な場面というよりも、山岳救助をする人たちの心の在りようとして、たくさんあって、読んで良かったと思った。
■ 『山靴を履いたお巡りさん』 岐阜県警察山岳警備隊 編
1992年、山と渓谷社より、山岳警備隊の本として二番目に出版されたこの本は、北アルプス飛騨側エリアの山岳救助活動をカバーする岐阜県警山岳警備隊の活動手記だ。
岐阜県警山岳警備隊は、1959年に誕生し、当初は富山や長野同様、民間救助隊に大きな協力を得、指導を乞いながら、徐々に山岳救助の技術を伸ばし、また、警察組織内でも隊員を増やし体制を整えていった。この時期、活躍したのは、鈴木釘夫氏(1937)、今井主憲氏(1947)、森本靖弘宏氏(1941)らである。
特に今井氏、森本氏は1960年代、民間救助隊からは警察警備隊が山でいったい何ができるのかと呆れられるほどの貧しい装備や技術を、がむしゃらに努力して、やがては民間救助隊と同等に連携し、さらには警備隊が独立して山岳救助ができるレベルまで、引っ張っていった警備隊内の実力者だったようだ。
1960年代の思い出話を読むと、隊員が集まって酒盛りをするとき、最後にはみんな裸になって円陣を組み、酔っ払いながらも山岳救助のあり方や技術について熱く討論したとか、登山屋にいって自腹で装備を揃える時に「いちばんいいピッケルを頼む」と、つい昨年だか一昨年だか前に流行った台詞そのままに頼み、一ヶ月分の給料が飛ぶような高価なピッケルを買ったりと、仕事という域を遙かに越えて、熱い思いを持って活動されていたらしい。
1975年には、現在も後輩指導に現役で活躍している谷口光洋氏(1956)が入隊し、隊は山岳救助活動に熱心に励んでいた。しかし、1977年5月4日、滝谷で二重遭難事故がおこり、長瀬隊員が殉死された。岐阜県警はこの二重遭難にショックを受け、滝谷での活動を自重するなど、山岳警備隊の活動に大きな制限をかけて、警備隊ができない活動は民間救助隊が担えばよしとした。
それまでは上昇志向だった岐阜県警山岳警備隊はこのとき、仲間の殉死のショック、組織からの圧力に力を落とし、活動が停滞気味になる。ちなみに、岐阜県警が本書を出すまでの殉死者はこのときの長瀬隊員のみで、毎年、丁寧な鎮魂参りが行われているのは、10/14に放映された谷口氏にスポットをあてた岐阜県警のドキュメンタリー番組でも紹介されていた。
岐阜県警は長野や富山の山岳警備隊と異なり、専門部隊ではなく、隊員がそれぞれ異なる業務を兼任したり、公務員として数年山岳警備隊を経験すると異動するといったデメリットもあったが、しかし、本書を読んでいると、力あり、熱意ある隊員によって、時には命がけの救助活動は、熱心に続けられていた。
この本に納められている数々の救助活動のエピソードは、北アルプス飛騨側の特性をあらわしていて、高い崖からの滑落、道迷い、そして豊富な水源が仇となりふだんはおだやかな川が雨による増水で荒れ狂い同時に何人もの登山者が命を落としたような事故など、さまざまなものがある。
そして、救助活動にあたるのも、警備隊だけではなく、後に配備されたヘリコプターの活躍や、提携する協力ドクターの活躍、また、山小屋経営者らいざとなれば民間救助隊となる人々との協同など、多くの人々のつながりがあってこそ、救助はまわってゆくということがわかった。
要救者にもさまざまな人が居て、1960-70年代には、山岳会などパーティーがかなりのところまで自力で遭難した仲間の救助をしようとする傾向があったが、道路や交通機関が整い出すにつれ、パーティーといっても、バラバラに行動するようなチーム力のない登山隊が増えてきたと記されている。
今は、もっと自己責任という題目のもと、パーティーがバラバラになる傾向に拍車がかかっていると思うので、パーティーのはずだったのに途中ではぐれ、単独で亡くなるケースなど増えているのではないだろうか。
登山の本を読んでいると、デメリットもあるけれど、やはりチームを組んで山をゆくことも、ひとつ登山の大きな醍醐味なのだから、今までの時代にない新しいつながりのチームでも、よりすばらしいチーム力を持って、登山をする時代にならないものかとわたしは思った。いや、わたしの伺い知らないところではもうそんなチームがいくつもあるのだろう。
もうひとつ、印象的だったのは、森本氏の発言なのだが、ヘリが導入されたことによるメリットデメリットだ。メリットとしてはもちろん危篤な要救者をあっという間に病院まで運べるというものがあるが、一方デメリットとして、遺体を収容した場合、麓で待つ家族の前にあまりに短時間に運びすぎるのではないかと危惧していた。
昔は人力搬送で、遭難現場から一日、二日と時間をかけて遺体を麓までおろしていて、その時間の中で、突然なくなった遭難者を受け入れる心の準備を家族は行っていたけれど、ヘリはその心の準備を行う時間を奪ってしまったのではないか、そして、その時間は案外、遺された家族にとってそれからを生きていくのに重要な時間だったのではないかとぽつりと記されていた。
それにしても、岐阜県警のこの本は、洗練された長野県警山岳警備隊や、霊山を多く頂き山に畏怖を持つ富山県警山岳警備隊と、少し性格がことなり、じつに人間として泥臭く、そこがいいのだ。たとえば女性の要救助者。若ければすれ違う一般登山者も手助けしてくれるだろう、しかしおばさんは誰も見向きもしないだろう。救助隊は仕事だからきちんと対応するけれど、といったことが書かれていた。
女性登山者(志望)かつ、これから中高年のレベルに入っていくわたしはなんだか悲しかったけれど、そういうこともストレートに書いてくれてあるので、遭難に対する心構えがきりりと引き締まったというのも事実だった。