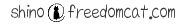2012年11月12日(Mon)
■ 『聖職の碑』新田次郎 著
大正2年8月26日、信州の伊那の里にある、尋常高等小学校の生徒ら37名が、伊那駒ヶ岳に向かい、天候が急変。11名の死者を出した。実際にあった遭難事故である。
これを題材に書かれた小説がこの『聖職の碑』だ。最初、わたしはこの小説を読むかどうか迷った。最初からわかっている悲劇。文庫本のページを繰るとすぐに、山の地図に、誰がどこで亡くなったかという×がついている。小学生の子を持つ親として、やはり、こどもが亡くなる話はつらい。どうしようか。どうしようか。迷いながらも、ページを繰り始めた。
話は大きく3部の構成で、そしてさらに1章分、著者の取材記がついている。1部は山へ行く前。登山を実施する学校の校風が、実践教育を教育の基とする赤羽校長と、新しい洋風な思想である白樺派を基にした自然教育を行いたい若手の教師たちとの、それぞれの理念が出会い、とまどいながらも、こどもたちを第一に考えて本当に良い教育を行いたいという思いのもと、前向きに描かれていた。
登山は、思想がどう揺れ動こうが、体験が人間を作る基礎となるという実践教育に重きを置く、赤羽校長から提案され、3回目の実施だった。教員や父兄の中には、修学旅行に3000m級の山行は厳しすぎるのではないかという批判もあったが、それでも、下見を遣い、持ち物、装備を丁寧に指導し、OBの青年会も同行する手はずを整え、観測所にも天候について問い合わせ、入念な準備をすることで、決行に至った。
ところが時代は大正2年、1913年である。装備も雨具は茣蓙や合羽、足下は草鞋。今のように羽毛のダウンやゴアテックの雨具があるわけではない。また天気予報も、今のように高気圧、低気圧、雨雲や台風進路がグラフィカルに描かれるものではない上、当時は台風という概念もなかった。台風はただ、韋駄天低気圧という低気圧でも強いものという認識だった。
2部は登山が開始され、一日目の目標の小屋につくあたりから暗雲が立ちこめる。麓では雲行きが怪しい程度だったのが、標高があがるにつれ強風となり台風が近づいてきたのだ。そこからはもう、壮絶な気象遭難の描写が続いていく。著者新田次郎氏は、富士山気象観測所にも勤務した経験があり、下界からは到底、想像もつかない山頂の嵐のさまをリアルに描写していくのだ。
そして、一人が倒れ、パニックを起こす集団…。あとはここで一人、ここで二人と、こどもたちが亡くなる様が痛々しい。最後まで力をふりしぼり、赤羽校長と付き添いの教員の、必死でこどもたちを守ろうとする極限の戦いもまた、つらい。結局、赤羽校長は、救助隊が来るまでは息があったものの、すぐに現場で息を引き取られてしまった。
3部は一人の教員が麓の村まで救助を要請に走り、救助活動が繰り広げられるところから、父兄の怒りが学校へ向かう対立を描く。また、現在も本当にある遭難碑の建立に奔走し、赤羽校長の教育理念を残すことに信念をかけた教員を描いている。
37名中11名が死亡する大遭難事故。現代ならば、このような事故があれば、学校は登山教育を中止するだろう。しかし、信州の周りは山に囲まれた伊那の里。山は暮らす人々にとって、分かちがたいものなのだ。そのため、しばらくは中止されていた登山も、やがて再開され、この事故を教訓に、登山を前提にしたカリキュラムが組まれ、現在もそれは続いているという。現在のカリキュラムは取材記に詳しく記されている。
ところで、わたしはこの本を読み終えて、自分を振り返り残念なことがあった。もっと前にこの本を読んでいれば。わたしはこどもを就学前に山へゆくカリキュラムをいれたところに通わせていた。この時のカリキュラムは駒ヶ岳のような高い山ではなく、穏やかな里山に続く低山だけれど、こどもたちが伝書鳩を持って登山してそこから放つというものだった。もし、この本をそれをする前に読んでいたら、教育と登山の意味の大きさを知り、もっともっと深い心で、こどもを送り出せただろうに。