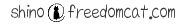2014年02月07日(Fri)
■ みことばの種 マルコ4章
マルコによる福音書4章は、ガリラヤ湖畔で大勢の群衆と、弟子たちに向かって、イエスが、神のみことばを植物の種などにたとえて、信仰と神の国について説いた箇所です。
3節から20節は、この世にまかれたみことばが信仰を持つ持たないは別にして、人々にどのような変化をもたらすかが、四つのたとえで語られます。
21-23節は、みことばを燭台にたとえて、その働きが隠されていることを明るみにだす性質があることを説いています。
24-25節では量りのたとえがでてきます。おそらくこれは天秤の量りで、片側に乗せる分銅が正しい分銅か、ズルをした分銅かを言っているのではないかと思いました。
また正しい分銅が何かと言えばこれはみことばなのかな、と。何かをはかるときには、自分勝手なデタラメなモノサシやはかりではなく、正しい分銅を用いることが大切ですね。使い方を習得するには、私のような音痴はなかなか難しいですが。
そして、再び、みことばを種にたとえた話が二つでてきます。このどちらも、神の国のたとえです。
26-29節では神の国は「ある人が地に種をまくようなものである」と言っています。種は人が意志を持ってまくけれど、その成長は意志を越えて、自然が育てあげ、そして、再び意志をもつ手で収穫されることが記されています。みことばを撒いた時、それが人の中でどう変化し育つのかは本当に神様しか取り扱うことのできない領域であることが示唆されています。
30-32節は神の国を一粒のからしだねにたとえています。からしだねはこれまでの文脈を見ると神の国であると同時にみことばと言っても良いかもしれません。
ここではどんな種よりも小さなからしだねが、まかれると成長して、鳥が宿にするほど大きくなると言っています。
小さな種が成長して、大きくなるだけではなく、他の命を守る宿になるというのです。
マルコによる福音書4章を読むと、種の生命力、命の生きる不思議、神の国の豊かさを知らされます。
自分はいばらに種をまいてないかなとか、呪詛のように宮沢賢治の春と修羅が蘇り、いちめんのいちめんの諂曲模様に、怒りの苦さや自責の念にとらわれたりもしますが、とりあえずそういうイメージは横において、からしだねが大きく成長し、鳥たちがそこに集まって囀っている風景をイメージします。
やまとうたは人の心をたねとしてよろづの言の葉となるのですが、神の国は神の心をたねとしてよろづのものが宿れる枝となるのです。これはまたヨハネ15章でわたしはぶどうの木とご自分をたとえられたイエスさまに繋がってゆきます。